幼稚園の毎日
2025/02/14
焚き火とコンテ画
今日は、年中さんが焚き火をしました。

昨日から、山に行ってたくさんの薪を集めてきました。
いきなり太い木に火はつかないんだよ、と実演し、焚き火の方法を説明します。
まずは太い薪を組んで、そこに全員で丸めた新聞紙を入れ、葉っぱや小枝を入れ、その上に中くらいの薪を乗せ…と準備します。
組み終わったら、フリーフローフライの歌を歌って、点火!
どんどん燃えてきます。

ただ見るだけではなく、音やにおい、熱なども感じます。
音を感じる時は、「静かにすると音も聴こえるよ、はい、静かに!」と声をかけると
いつも静かになることのないくらいの年中さん、シーーーーーーン…となりました。
そうすると、パチパチ、シューシュー、いろんな音が聴こえます。
耳を澄ませました。
その後「やきいもの時と違って、パン!って音が聴こえないのはなんで?」と質問。
なんでだと思う?とクイズをして、「竹が入ってないから」という答えを伝えます。
そして、「じゃあ竹を入れてみよう」と入れてみると、みんなが音に集中。
そのうち、「パン!」と節が弾ける音が聴こえました。
「竹の中の空気が熱くなって膨らんで、風船が割れるみたいに弾けるんだよ」とも伝えました。
体験する理科ですね。
そうやって焚き火をいっぱい感じたあとは…

すぐにお部屋で、コンテ画を描きます。
焚き火をいっぱい感じた直後、感覚が新鮮なうちに!

焚き火からインプットしたものを、コンテ画でアウトプットします。
焚き火(炎)という、固定された形のないものを描く、という課題と
コンテという、初めて使う画材の組み合わせは、相性がとても面白いです。

必然的に、概念画にならずに、個人の感性で絵を描くことになります。
これが面白い。
概念的な絵(地面の線を描いてチューリップ生やして空に太陽を描くみたいな)になりがちな年中さんだからこそ、それをあえて崩して表現の楽しさを感じます。
縛られるものもないので、かなり積極的に描いていましたよ!

描いた絵を説明してくれています。
こちらのコンテ画も、お部屋に掲示しますので、よかったらまた見てくださいね。
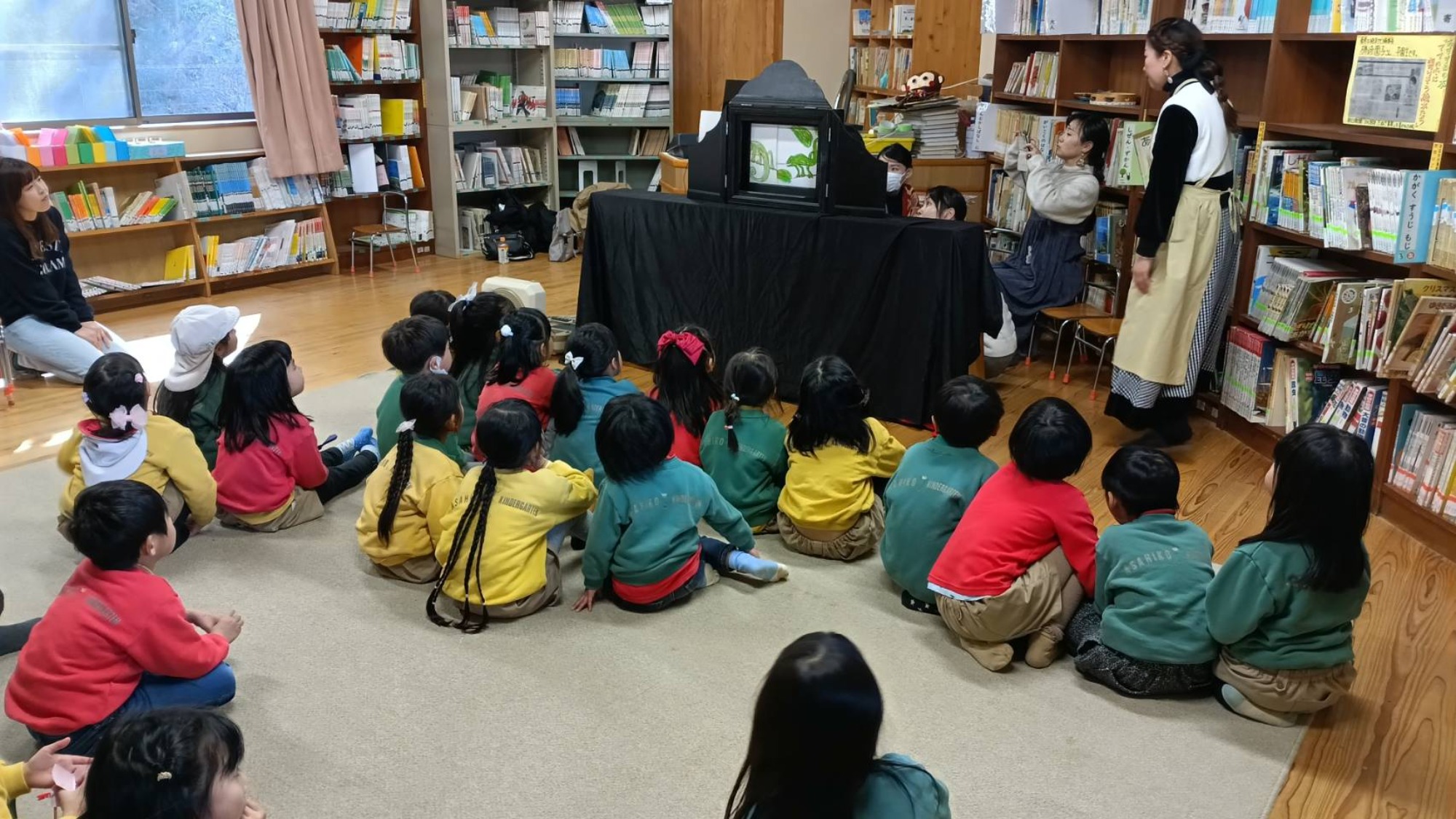
午後は、年長さん、図書ボラ「さるさる一座」の読み聞かせ。

こういった、日常の中にあった活動も、すべて「あと〇回だね」「最後だね」となっていくのが、卒園間近の年長さん。
図書ボラ読み聞かせも、残すところあと一回のみです。
次も楽しみだね!
追伸
そういえば、みずいろぐみの発表会のラストのカーテンコールは、こどもたちから「さるさる一座みたいなやつやりたい!」と発案され、ああなったそうですよ。
繋がってますね!

